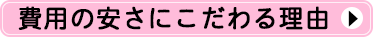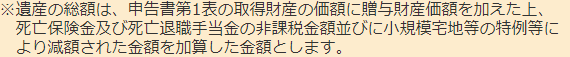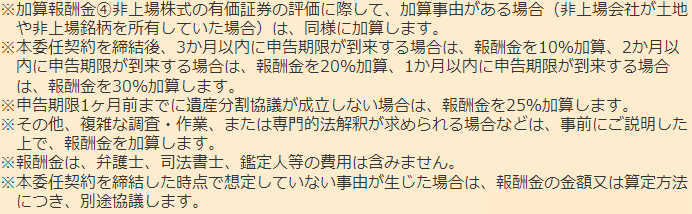生命保険による相続税対策とはどのようなものですか?
1 生命保険を利用することで相続税を節税できる可能性があります
生命保険金は、民法上は相続財産には含まれませんが、相続税の計算においてはみなし相続財産として課税の対象に含まれます。
ただし、生命保険金は相続人の生活の保障のために存在しているという観点から、非課税制度が設けられています。
この制度を利用し、相続税の節税をすることができる可能性があります。
以下、詳しく説明します。
2 生命保険金の非課税枠と計算方法
生命保険金の非課税枠は、次の計算式によって求められます。
生命保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に算入できる養子の数には制限があります。
原則として、被相続人に実子がいる場合は1人、被相続人に実子がいない場合には2人までとなります。
特別養子縁組を行った場合や、配偶者の連れ子を養子にした場合は、実子とみなされます。
相続放棄した人がいても、その放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めることができます。
相続放棄した元相続人の方や、相続人以外の方が生命保険金を取得した場合は、この非課税枠の適用を受けることができないので注意が必要です。
3 各相続人の非課税額の計算
各相続人が受け取った生命保険金の合計額が、2の非課税限度額以下である場合には、生命保険金は全額非課税となります。
各続人が受け取った生命保険金の合計額が、非課税限度額を上回る場合には、各相続人の非課税限度額は次の計算式で求められます。
各相続人の非課税限度額 = 非課税限度額 ×(特定の相続人が受け取った生命保険金の金額)÷(相続人全員が受け取った生命保険金の合計額)
4 非課税制度の対象になる生命保険について
生命保険金は、契約の内容によって課税される税金が異なるため、注意が必要です。
相続税の非課税制度の対象になる生命保険は、被保険者と保険契約者が同じで受取人が異なるという内容の生命保険ですので、しっかりと保険証書や支払通知書の内容を確認しましょう。
相続税の申告をすると必ず税務調査が行われますか? 相続税の書面添付制度に関するQ&A