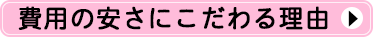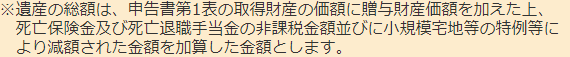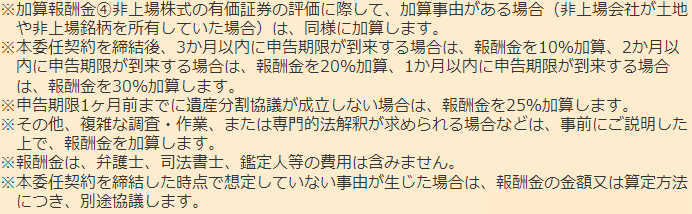お役立ち情報
相続税の更正の請求とは
1 相続税の更生の請求
何らかの事情によって相続税を納め過ぎている状態になってしまった場合(本来納めるべき金額よりも、納めた相続税が多くなった場合)、一定の手続をすることで、払い過ぎの状態になっていた分の還付を受けることができます。
この手続のことを、相続税の更生の請求といいます。
更生の請求は、法律どおりに税額の計算ができていなかった場合に用いることができる手続です。
実務上は、遺産分割に争いがあって未分割申告をせざるを得なかった場合に、遺産分割協議成立後に行われるというケースも多くみられます。
更生の請求は、場面によってできる期間が異なることもあり、注意が必要です。
以下、更生の請求ができる期間、更生の請求の手続きについて具体的に説明します。
2 更生の請求ができる期間
更生の請求には期限が設けられており、原則として、相続の開始を知った日(一般的に被相続人が亡くなった日)から5年10か月です。
一定の事由が原因で相続税の更生の請求をする場合には、相続の開始を知った日から5年10か月を過ぎていても更生の請求はできます。
しかし、当該事由が発生した日の翌日から4か月以内(相続の開始を知った日5年10か月以内であっても)に、更生の請求をしなければなりならないという特則が設けられています。
一定の事由の代表的なものは次のとおりであり、いずれも相続と密接な事由であることから、更生の請求ができる期間には注意を払う必要があります。
- ①未分割の財産が分割された(遺産分割協議等の成立)
- ②認知、廃除等による相続人の異動
- ③遺留分侵害額請求権の行使
- ④遺贈する旨の遺言書が発見された又は遺贈が放棄された
【参考条文】
(更正の請求の特則)
第三十二条 相続税又は贈与税について申告書を提出した者又は決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する事由により当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後修正申告書の提出又は更正があつた場合には、当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格及び相続税額又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)をすることができる。
一 第五十五条の規定により分割されていない財産について民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後当該財産の分割が行われ、共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。
二 民法第七百八十七条(認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで(推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条(相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)の規定による相続の放棄の取消しその他の事由により相続人に異動を生じたこと。
三 遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。
四 遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。
(第5号以下略)
3 更正の請求の手続き
相続税の更生の請求をするためには、相続税の更正の請求書と、更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等が必要となります。
更正の請求の理由の基礎となる事実を証明する書類等とは、典型的なものとしては、未分割申告後に遺産分割協議が成立したことを示す遺産分割協議書や遺産分割調停の調書です。
国税庁のウェブサイトにおいても、詳しい案内が記載されており、相続税の更生の請求書のフォーマットも提供されています。
参考リンク:国税庁(相続税及び贈与税の更正の請求手続)
必要な書類が揃いましたら、管轄の税務署に提出します。
更生の請求の内容に問題がない場合には、相続税の更正通知書が交付され、その後国税還付金振込通知書を受け取ると、還付された相続税が指定の口座に振り込まれます。
相続税対策として遺言を作成するメリット マンションを相続した場合の相続税評価