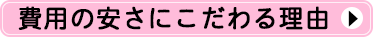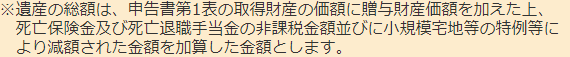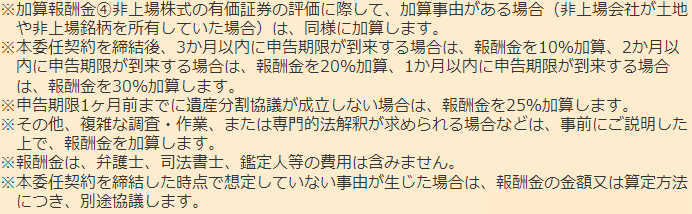お役立ち情報
相続税の申告に必要な書類
1 相続税申告に必要な書類は大きく分けて3種類
相続税の申告に必要な書類は大きく分けて、相続税申告書、相続関係資料、財産関係資料の3種類があります。
相続税申告書は、相続税の申告をするにあたって作成する書類です。
相続税申告書等の様式は、国税庁のホームページで確認・ダウンロードすることができます。
参考リンク:国税庁・相続税の申告手続
相続関係資料とは、被相続人と相続人を証明するための資料です。
財産関係資料は、被相続人の相続財産の内容を裏付ける資料です。
以下では、相続関係資料と財産関係資料について、それぞれ詳しく説明します。
2 相続関係に関する資料
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人の現在の戸籍謄本の写しが必要となります。
これらの戸籍謄本の束に代えて、法務局で発行を受けることができる法定相続情報一覧図の写しを用いることもできます。
これらの資料は、被相続人が亡くなったこと、およびすべての相続人を税務署に対して示す(法定相続人の人数で相続税額が変わります)ために必要となります。
また、相続人のマイナンバーカード、または身分証明書と通知カードの写しも必要です。
戸籍謄本は、市町村等の自治体の役所等で取得することができます。
3 財産関係資料
⑴ 遺言書または遺産分割協議書
まず、遺言書がある場合には、遺言書の写しを用意します。
遺言書がなく、かつ相続人が複数いる場合には、遺産分割協議書の写しと、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。
⑵ 預貯金通帳、残高証明書等
基本的には、被相続人の死亡日時点の残高が記載された預金通帳の写しを用意します。
預金通帳がない場合には、銀行等で残高証明書を取得します。
預貯金については、死亡前3年間の履歴、できれば死亡前5年間の履歴を用意します。
定期預金がある場合には、既経過利息計算書も必要となりますので注意が必要です。
⑶ 不動産関連資料
まず、法務局で土地・建物の登記事項証明書を取得するか、または登記情報提供サービスで登記情報を取得します。
建物については、評価額を示すための資料として、相続が発生した日の属する年度の固定資産評価証明書または名寄帳を用意します。
土地については、路線価地域の場合は、評価額を示すための資料として、公図または地積測量図、路線価図を用意します。
倍率地域の場合は、評価額を示すための書類として、固定資産評価証明書または名寄帳を用意します。
被相続人が不動産を貸していた場合、または借りていた場合、評価額に影響することから、賃貸・賃借の事実を示すため、賃貸借契約書等の写しも必要です。
⑷ 有価証券関連資料
上場株式や投資信託がある場合には、被相続人死亡時点の残高証明書を取得します。
金融機関によっては、相続税申告用の評価額も記載していることがあります。
非上場株式がある場合には、株式の評価額を算定するため、当該株式会社の決算書や税金の申告書の写しが必要です。
⑸ 死亡保険金関連資料
相続人が受け取った死亡保険金は、民法上は相続財産には含まれませんが、相続税申告においてはみなし相続財産として扱われ、課税の対象になります。
死亡保険金の金額を示すための資料として、生命保険支払通知書が必要になります。
⑹ 事業用資産関連資料
被相続人が個人事業主であった場合には、事業用の器材や在庫商品など、財産価値のある事業用資産が遺産に含まれることもあります。
そのため、被相続人の確定申告時の決算書や、業務用の帳簿を確認し、必要に応じて提出します。
⑺ 葬儀費・債務関連資料
葬儀費と、被相続人の債務は、相続財産の評価額から控除することができるため、相続税を低減する効果があります。
葬儀費に関しては、葬儀会社や火葬場の領収書、お布施の領収書(ない場合にはお寺等の名称・住所と金額のメモ)、心付けのメモ等を用意します。
債務については、借入金の残高証明書、未納の税金等の通知書、被相続人死亡時点で未払いであった医療費や公共料金の請求書等を用意します。
配偶者に対する相続税額の軽減 相続税申告における不動産の評価方法