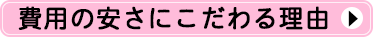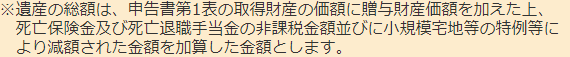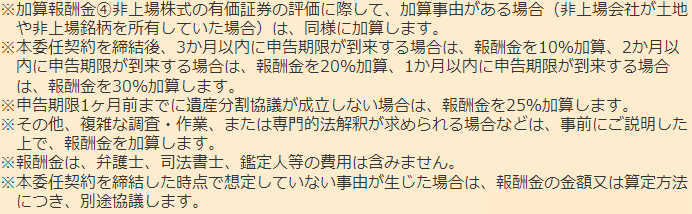お役立ち情報
不動産を活用した相続税対策の注意点
1 不動産を活用した相続税対策には注意が必要
相続税は、相続財産に対して課せられる税金です。
正確には、相続財産の評価額に対して一定の税率を掛け合わせる等の計算をして求められた税額を収める必要があります。
つまり、一般的には、相続財産の評価額が低ければ低くなるほど、相続税の税額も低くなります。
相続税を計算する際の財産の評価において、不動産の評価額は、市場価格と比較して低く評価される傾向があります。
例えば、土地を評価する際に用いられる相続税路線価は、市場価格と比較して低廉であることが多くあります。
また、不動産を貸し付けることで、借家権割合や借地権割合を控除することができるので、さらに評価額が低減されます。
このように、不動産を活用することで、相続税を節税することができるようになります。
もっとも、不動産による相続税対策をやりすぎてしまうと、遺産が不動産ばかりになってしまい、相続税の納税資金を用意できなくなってしまったり、遺産分割が困難になってしまったりすることがあります。
また、実際の申告の際に節税が認められなくなるケースもありますので、注意が必要です。
以下、これらの注意点について詳しく説明します。
2 相続税の納税資金を用意できなくなってしまうことがある
相続税は、原則として金銭で納める必要があります。
一般的には、金融機関の窓口に納付書を提出し、振り込む形で納税することが多いです。
相続税を節税するため、現金や預貯金の大半を不動産に変えてしまうと、相続が発生した際に、相続人が取得する現金や預貯金が減ってしまいます。
相続人がもともと現金や預貯金を潤沢に持っている場合には問題ありませんが、そうでない場合には、不動産を売却しないと納税資金が用意できないという事態に陥るおそれがあります。
3 遺産分割が困難になる
不動産は、一般的には均等に分割して相続することが難しい財産です。
相続財産の大半が不動産である場合、不動産を取得した相続人が他の相続人に対して代償金を支払うか、売却換価して売却金を相続人間で分配するか、共有状態のままにするという分割方法で遺産分割を行う必要があります。
不動産の分割方法は、相続人間で話がまとまりにくい類型のものであり、遺産分割協議が難航するおそれがあります。
4 実際の申告の際に節税が認められなくなることもある
一般的には、現金や預貯金を不動産に換えることで、相続財産の評価額を低減することができます。
しかし、あからさまに節税を目的とした不動産購入を行っていたような場合には、一般的に用いられている路線価や固定資産評価額による評価ではなく、市場価格に近い評価とされる可能性があります。
令和4年4月19日の最高裁判決において、このような趣旨の判決がなされました。
参考リンク:最高裁判所判例集
節税対策を行う方が相当高齢であるような場合や、不動産購入に充てる資金が多額である場合などには、節税につながるかどうかを事前に検討しておく必要があります。